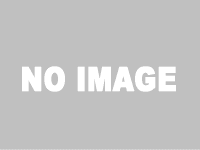| KING CRIMSON |
DETAILS >>
|
|
ORIGINAL STUDIO ALBUMS ■ALBUM /ARTIST [XXXX] ■ALBUM /ARTIST [XXXX] ■ALBUM /ARTIST [XXXX] ■ALBUM /ARTIST [XXXX] ■ALBUM /ARTIST [XXXX] OTHER ALBUMS >>
|
| ■ALBUM [XXXX] | ||
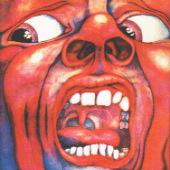 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| この作品をリリースするに当って、クリムゾンの前身バンドであるGiles, Giles
& Frippにおいての激しいメンバーチェンジや当初プロデュースに当ったトニー・クラークがこの作品のレコーディングに失敗するなどの困難があったそうだけど、それを乗り越えてちょっとした難産のリリースとなった作品。レコーディングに関してはかなりゴタゴタしたようで、マスターテープを一度破棄し全くの白紙に戻してしまう事態にもなったらしいですね。 本作はクリムゾンの代表作として名が挙がる事が多い作品。いわゆる名盤として語られています。01のスリリングな展開から静を強調した美しい曲へと繋がっていくアルバム構成も含めてとても評判が良いです。これを酷評しているレビューは少なくとも俺は見たことがないなあ。 で、本作を語る場合に1996年10月10日にイギリスで発売されビートルズのアビイロードを抜いて全英トップのセールスを記録した・・・・・という書き出しで書き出すのは今更どうなんだろうね。実際今となってはどうでもいい情報だよね。後追いで聴き始めたならなおの事。ともかくこれがクリムゾンの記念すべきデビューアルバムであり、現在でも彼らの代表作の1つとして語り継がれている作品なのです。 何と言っても01の『21st Century Schizoid Man』が目玉となる曲であるのは間違いないね。7分半に及ぶ大曲でヘヴィーメタル的な壮大さを持っている曲。歌は最初と最後にチョコっと入っている程度でメロディーを楽しむ曲ではなく中盤での緊張感溢れるインスト部分が最大の聴き所となっている曲と言えます。この曲のインパクトはジャケットのイラストと同様にいつまでも色あせる事は無いでしょう。一度聴いただけで充分に伝わるであろうインパクトを備えている曲ですね。その点では非常に分かりやすいところに魅力がある曲。 今でこそクリムゾン=ロバート・フリップというイメージが強いけど、この時点ではギタリストのロバート・フリップよりもイアン・マクドナルドが音楽的主導権を握っている感が強くて、世間で言われているほどギターのサウンドが目立つ音作りだとは思いません。確かに01の世界観はメタルに通じる要素が多いのは確かだけど、それ以外の曲は全く違うテイストで構成されている作品だよ。因みに02はなんとロバート・フリップのクレジットが無い曲でそれはクリムゾン史上で後にも先にもその曲だけです。 某HM/HR系雑誌において、このアルバムはとてもヘヴィーメタル的な作品なのでとても入りやすいなどと書かれていました。だから俺はそういうイメージを持ってこの作品を手に取ったのね。俺のクリムゾンへの入り口はこのアルバムだったのよ。だけど実際に聴いてみると01以外は非常に美しく透明感のあるものでかなり戸惑ったのを良く覚えてるよ。01以外の曲は当時メタル小僧だった僕の耳にはすんなり馴染まなかったな。本格的に全ての曲を好きになったのはそれから随分後のことです。 イアン・マクドナルドが一人でこなすサックス、フルート、キーボード、メロトロンなどのような楽器群の方がサウンドの中核を担っている印象が強くて、01以外の曲はとにかく美しく仕上がっていて歌のメロディーも01とは違った壮大さがあります。じっくり聴いていると深い海のそこに静かに沈んでいくような気分になるっつうか。俺個人は01以外の曲を理解するのには随分と時間がかかったけど、作品全体を好きになった今は本当にどの曲も素晴らしい出来だと思います。 ただ04『Moonchild』の後半部分が意味不明で退屈なインプロヴィゼイション(即興演奏)になっていて、しかもそのパートが無駄に長いのがツライ。俺は04の後半部分は飛ばして聴く事が多いね。さすがにこれは聴いてるの退屈だよ。04の前半部分は歌モノとなっていて歌のメロディーが素晴らしいし、曲の雰囲気も透明感がってとても美しいけど後半部分がそれを台無しにしているんだよね。後半部分はそもそも音楽になっていないもん。『音』がただポロンポロンと鳴っているのが延々繰り返されているの。俺にはそのパートを理解する事が出来ないし無理して聴こうととも思わない。この作品においての唯一の欠点はその部分だね。その退屈な部分は実は後から無理やり付け加えたものなんだそうで。収録時間を延ばすために無理に加えたんだと。意味ないよなあと思いつつ『あ、それであんなに意味がわからないのか』と納得したりもしたけど。 01のインパクトと威圧感で幕を開け02、03、04で静の美しさで静かに深海に沈んでいくような感覚を表現し、05で壮大に幕を閉じるこの作品はクリムゾンの代表作の名に相応しい名作だよ。最初から最後まで流れが考えられている構成が良いんだよね。ロック作品というよりも一本の映画を見せられてるような、何か壮大な神話か何かのサウンドトラックのような雰囲気を醸し出す本当に妙な世界がここにあります。04の後半を除けばね。それさえ無ければ完璧な作品だったのにねー。 【Personnel】-------------------- Robert Fripp [Guitar] Ian McDonald [reeds, woodwind, vives, keyboards, mellotron, vocals] Greg Lake [bass guitar, lead vocals] Michael Giles [drums, percussion, vocals] Peter Sinfield [words and illumination] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
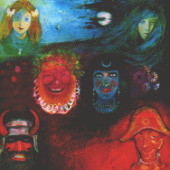 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 過渡期とされる時期に発表された二作目。前作の成功によりかなり製作を急がされた上に、ここでイアン・マクドナルド、グレッグ・レイク、ピーター・ジェイルズが脱退してしまう(サポートメンバーとしては参加した)など、かなりバタバタした状態で製作されました。ジェイルス兄弟、グレッグ・レイク、キース・ティペット、メル・コリンズ、ゴードン・ハスケルはセッション・ミュージシャンのような形での参加なのであまり『バンド』としての作品とは言い難いようですね。 本作はマニアの間では非常に評判が悪いです。名作とされる前作とアルバムの流れが同じである事がその主な原因。01〜04までの流れが明らかに前作を踏襲しているのは事実です。01は02のイントロ的な曲なので02と一組として考えるとして、01〜02は前作で言うところの『21st Century Schizoid Man』にあたる曲。曲構成が非常に似ているのよ。 アルバム全体の構成も似ていて、『21st Century Schizoid Man』的な『Pictures Of A City』の後に静の曲『Cadence And Cascade』を持って来ていて、さらにその後に前作の03『Epitaph』風の『In The Wake Of Poseidon』が来るといった具合。そこがこのアルバムの批判要素である場合が殆どで『ファーストの二番煎じ』、『過渡期で無理矢理作ったようだ』などと言われています。ただし後半部分は少し違うモノとなっているけどね。 そんな理由からマニアの間では非常に評判が悪いわけなんだけど俺はそんなに悪い作品としては捉えていないな。むしろ結構好きですね。バタバタした特に時期に発表されたのが影響してか、前作の極上の美しさや壮大さ、緊張感には到底おいつけていないとは思うけど前作が凄すぎたというだけでこのアルバムはこのアルバムでなかなか悪くないよ。 確かに構成は似ているけど俺には逆にそれがポイントとなって意外とすんなり入る事が出来ましたね。01はイントロとしての機能しか果していない曲なので実質02がオープニングを飾る曲といえるのだけど、その02は間違い無く『21st Century Schizoid Man』を基盤として創られているのは確か。だけど単独の曲として充分魅力のある作品だと思ってます。『21st Century Schizoid Man』ほどの高揚感は無いけど単純にカッコイイ曲なので俺は凄く気に入っているよ。 03『Cadence And Cascade』は前作の『I Talk To The Wind』に当る曲で静の部分が強調された美しい曲。メロディーがとても良いと思うね。04『In The Wake Of Poseidon』は前作の『Epitaph』に当る曲。『Epitaph』同様静の美しさと壮大な雰囲気が融合したタイプの曲。双方の曲の導入部はかなり似ているがもちろんメロディーは違うものだし、俺はとくに気にならないので双方とも好きな曲です。 05『Peace - A Theme』は01をアコースティックギターで表現したつなぎの曲。これがなかなか良いのよ。この曲でのフリップのギターはとても表情豊かでとても美しいです。凄く巧いと思う。そして06『Cat Food』は妖しいピアノが印象的な曲で前作には無かったタイプの曲。クリムゾンのポップでメロディアスな面が強調された名曲です。この作品ではこの曲がある意味目玉かもしれないね。ジャズ的であると同時に非常に妖しい曲に仕上がっていて素晴らしいと思う。俺は生粋のジャズというものを聴く人間では無いけどジャズで聴く事の出来る音の見事な外し具合というのがこの曲ではとても活きているね。 07『The Devil's Triangle』は11分を超える壮大な組曲。実はこの曲が原因で俺はこのアルバムになかなかは入れなかったという過去があります。今でこそこのアルバムは好きな作品と言えるんだけど、初めて聴いたときはこの07が死ぬほど退屈に思えました。前作と構成が似てるアルバム前半部分はすんなり入れたんだけどね。この曲は同じ調子で延々と繰り返される曲調がどうにも退屈。俺がこのアルバムで一番最初に気に食わなかったのは前作を踏襲した構成ではなく、この07の存在でしたね。 3分以上もかけて徐々にフェイドインして来て、あとは怪獣映画のサントラのような、ゴジラが街に襲撃して来る時に流れそうな行進曲みたいなフレーズの繰り返しが続くのでつまらない曲と言えばつまらない曲だし(実際つまんないと俺は思うよ)、特筆するような要素を含む曲でも無いです。なんとなく危機迫るような雰囲気は出ているのでこの単調な繰り返しを心地よく思えれば楽しめるのかな。まあ今では最初ほど退屈には思わないけどやっぱ好きな曲ではないな。で、総合すると全然ダメなアルバムだとは思わないというのが結論。 けど初心者はやっぱこれを最初に聴くのはやめたほうが良いでしょうね。 【Personnel】-------------------- Robert Fripp [Guitar, Mellotron, & Devices] Greg Lake [Vocals] Michael Giles [Drums] Peter Giles [Bass] Keith Tippett [Piano] Mel Collins [Saxes & Flute] Gordon Haskell [Vocal] Peter Sinfield [Words] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
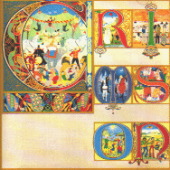 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| セカンド同様かなりバタバタした時期にリリースされたサードアルバム。前作『
In The Wake Of Poseidon 』のリリース直後から既にこの作品の為のリハーサルが開始されていて、前作がリリースされた3ヶ月後にはもうレコーディングを開始。同年12月にはリリースされるというハイペースで世に出た作品です。この作品が製作された背景にある大きな特徴のひとつはゲストで参加したミュージシャンが非常に多い事が挙げられます。リリース直前にゴードン・ハスケルが脱退したなどの関係で、この作品のリリース後には一度だけBBCのテレビ出演でのステージ以外ではライブは行われていないらしいです。その時の音源は正に幻のようで、現在に至るまでブートなどとしても市場には出回っていないとの事。俺的には別にどっちでも良いけど。 因みに05『Lizard』の最初のパートである『Prince Rupert Awakes』は初代ガンダムの映画の挿入歌である『ビギニング』の元ネタです。まるっきりパクリ。演奏のピアノは全く同じと言っても過言では無い勢いだし、メロディーも違うことは違うけどソックリだし、サビへの流れもソックリ。何処かで『ビギニング』を聴く機会があれば比べてみると面白いよ。ホント『まんま』だから。 で、前作同様本作もマニアの間では非常に評判が悪いです。その主な原因としては、ゴードン・ハスケルの歌の下手さ、ゲストミュージシャンの節操のない多さなどが挙げられます。特にハスケルの歌の下手さへの風当りはかなりものものようですね。その反面、前作『In the Wake of Poseidon』における批判原因だった『二番煎じ』的な批判は一切無く『新しい試みをしている』などという言われ方もしているので、独創性があるという点では評価されている向きもあるみたね。 そんな感じで評判の良くない本作ですがアンディー・マカロックのドラムプレイが非常に活きていて俺は大好きな作品です。一般的な評価とは大分かけ離れた評価となってしまったけど好きなんだもん。仕方ないじゃん。これは前作とは違ってこのアルバムだけの世界観を持った独立した作品に仕上がっているし、前作までの美しさや不気味さも兼ね備えているとても素晴らしいと作品だと思うんだけどな。非常に『妖しい』作品ではあるけどね。 ゴードン・ハスケルの歌がヘタクソだって相当言われてるようだけど俺は全然気になりません。というかそういう意見を後から目にして『ああ、言われてみれば巧くないかも』程度に感じただけで最初はそんなこと微塵も思わなかったし、歌の下手さ加減が問題になるようなつくりでも無いよ。そもそもヴォーカルの録音自体にかなりエフェクトをかけてある部分が多く『これはこれでこういうもの』という意識しかしていないですね。 そのエフェクトは効果を出すためというよりも歌の下手さを誤魔化すためのモノと言われたら確かにそうなのかもしれないです。となると、俺はその誤魔化しに見事に誤魔化された一人なんでしょうね。05『Lizard』においての冒頭のメロディーが素晴らしいパート『Prince Rupert Awakes』では歌が非常に大事な役割を果すと思うけど、ここではイエスのジョン・アンダーソンが歌っているので問題ないし。それじゃあバンドとしてどーなの?というのは確かに感じるけどさ。 作風としての大きな特徴はジャズ度の高さだと思います。ヘヴィーメタルとの共通性をよく指摘されるクリムゾンですけど、この作品においてはそのようなカラーは全くと言って良いほど感じられません。かなりジャズ的なアプローチがなされていて歪んだギターなどは殆ど聴く事が出来きません。ゲストで参加したミュージシャンが多い事からかなり色々な楽器の音が入り乱れているある意味豪華な作りだね。 ジャズ度を大きく上昇させている要因はドラムのアンディー・マカロックのプレイ。とても細かく手数の多いフリージャズ的なスタイルがとても心地よいです。01の『Cirkus』でのプレイも素晴らしいと思う。この曲はとても不気味で独創性に溢れていいますね。本当に不気味だよコレは。この曲は過渡期を越えて第2期と言われる時期にライブでの定番曲となっていて、クリムゾンとしてもそれなりに大事にされている曲ですが俺自身にとっても大事な曲。02以降も好きな曲ばかりだな。 ただ05『Lizard』は少し長すぎるとは思う。20分以上もある曲なんですけど明確にパートが分かれているのであえて1曲としてまとめないでパートごとに別の曲として分けて欲しかった気もするな。分かれてないと聴くのが億劫になるんだよな。前半のジョン・アンダーソンが歌う美しいメロディーは素晴らしいし、中盤のキャッチーなインストパートも好きだけどやっぱり長すぎるという気はするね。中盤のキャッチーさのあるインストパートは近年発表されたドリーム・シアターのアルバム『Six Degrees Of Inner Turblence』収録のタイトル曲の最初のパートに通じる聴きやすさがあるけど、ドリーム・シアターのあの曲はこの辺りから影響を受けているのかもしれないね。 何度聴いても一般的にどうしてそこまで批判されるのが分からなくなる、俺にとってはクリムゾン過渡期から生まれた見事な名盤です。 【Personnel】-------------------- 正規メンバー Robert Fripp[Guitar, Mellotron, Electric Keyboards & Devices] Mel Collins [Saxes & Flute] Gordon Haskell [Bass Guitar & Vocals] Andy McCulloch [Drums] Peter Sinfield [Words & Pictures] ゲストメンバー Robin Miller [Oboe & Cor Anglais] Mark Charig [Cornet] Nick Evans [Trombone] Keith Tippett [Piano & Electric Piano] Jon Anderson of YES [Vocals on 『Prince Rupert Awakes』] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 前作のリザード同様過渡期とされる時期にリリースされた4作目。リザードのリリース後にヴォーカル&ベースのハスケルが脱退した事によりライブ活動が出来なくなったらしく急遽オーディションをしボズが加入。彼は元々はベースが弾けなくて、フリップが2ヶ月間の猛特訓でベースを彼に叩きこんだらしいんだけど、ホントなのかなあ。この作品でドラムを叩いているブライアン・フェリーは、元々ヴォーカルのオーディションに参加したらしいがドラマーとして採用されたとの事。その為にアンディー・マカロックはクビとなってしまいました。プロの世界は厳しいね。 その後バンドは1971年4月12日にフランクフルトで1年半弱ぶりにステージに立ったのを皮切りにツアーを開始し同年6月2日でそのツアーは終了。その後、この作品のリハーサルとレコーディングを開始。さらにイギリス内でのツアーと平行してレコーディングが行われて12月3日にリリースとなりました。リリース後のこの作品の為のアメリカ・ツアー後にシンフィールドはバンドを脱退します。 この作品は現行のモノと以前のモノとで内容が少し異なる所があります。現行のバージョンである『30th Anniversary Edition』ではオリジナル通りの仕様で06『Islands』の後にリハーサル時の音がクレジット無しで収録されていますが、俺の持っている『The Definitive Edition』ではその部分カットされてます。なので俺はその部分は未聴。あんまり興味ないからこれからもそこは未聴のままでしょう。 本作はクリムゾン至上でもっとも静かな作品です。ジャケット写真の雰囲気がそのまま音に現れているかのような広くて静かな宇宙空間に深く深く飲み込まれていくような、もしくは深海に沈んでいくような感覚を覚える作品となっています。この作品はヘッドフォンで楽しみたいね。逆に言えばヘッドフォンでじっくり聴かないとサラっと流れて行ってしまう作風なんだけど。聴いてて眠くなる人は眠くなるよきっと。 前作と同様にヘヴィーメタル的な要素は全く感じないけど、この作品ではフリップのギタープレイが何処と無くブルーズがかっているのが特徴だね。静かな曲調の中に強烈に歪むギターが被さる場面もあるし、よく聴くと実はかなり表情豊かな作品です。前作のような多くの楽器が音が入り乱れるような場面は無いにしろ、静かだからと言って決して無表情な内容では無いよ。 01『Formentera Lady』は不気味とも美しいとも言えるような曲で前半はハッキリとしたリズムがないような浮遊感を感じるパート。この曲はこの作品の世界感を象徴しているかのよう。ゆっくりとゆっくりと深海に沈んでいくような雰囲気。後半部分では少しリズムが刻まれつつ02『Sailor's Tale』へと繋がっていきます。01と02は完全に繋がっているので合わせて一曲って感じだね。ただ聴いていてもどこで次の曲になったのか気づかないほどだよ。 01〜02の中盤までは本当に静かに進行していくのでじっくり聴かないとただのBGMになってしまうけど、02は途中からジャズっぽいパートへと変化して静かな中に激しさも併せ持つような展開をするのが良いね。その部分が秀逸。前半部分の静かなパートも後半の展開があるからこそ活きてくるという風に思います。01〜02はこのアルバムで一番好きな流れ。イアン・ウォーレスのドラムもなかなか良いな。でも前作でドラムを叩いていたアンディー・マカロックの手数の多いドラムが好きだった俺は、マカロックがこの曲でドラムを叩いていたらもっとカッコよくなったんでは無いかと少し残念でもあるけど。なんで彼は巧いのにクビになったのだろうね。 03『The Letters』はひとつひとつの展開が唐突で最初から最後までどんな曲なのか掴みにくい曲だけど、その掴めない展開が逆に魅力になっている感じ。04『Ladies Of The Road』はサックスがやけに目立つ形で取り上げられているのが印象的。クリムゾンには珍しい感じのコーラスも面白いね。激しく無いのに全体的に乱暴な感じが漂うという妙な曲で前作の雰囲気を継承した曲じゃないかな。 05『Prelude: Song Of The Gulls』はクラシカルな曲だけど、メロディーが綺麗で聴きやすくまとまっているので違和感なく楽しめました。この作品の流れに上手く馴染んでいると思います。『Lizard』収録のタイトル曲『Lizard』の中間部分のインストパートと通じるモノがある曲なので、この曲もドリーム・シアターの『Six Degrees Of Inner Turblence』収録のタイトル曲の最初のパートに通じる聴きやすさがありますね。あの曲が好きならこれも馴染めるはず。06『Islands』は終始静かに美しく語りかけるように進む曲。美しい曲だとは思うけど俺には少しかったるいなあ。 全体としてはとにかく『静』の側面が強調された作品なので刺激は殆ど感じないけど、しっとりと世界に浸れるという意味ではなかなか優れた作品じゃないかな。でも、初期から70年代までの作品の中で一番聴く回数が少ないはこの作品だったりもするけど。本作はじっくり聴かないと本当にサラっと流れて行ってしまうので、気楽になかなか聴きはじめられないのよね。それなりに聴こう!という意思が必要というかさ。 初心者にはいきなり薦めるのは避けたい作品かな。 【Personnel】------------------- 正規メンバー Robert Fripp [guitar, mellotron, Peter's Pedal Harmonium and sundry implements] Mel Collins [flute, bass flute, saxes and vocals] Boz [bass guitar, lead vocals and choreography] Ian Wallace [drums, percussion and vocal] Peter Sinfield [words, sounds and visions] ゲストメンバー Keith Tippett [piano] Paulina Lucas [soprano] Robin Miller [oboe] Mark Charig [cornet] Harry Miller [string bass] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
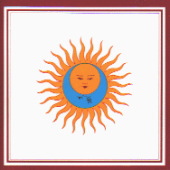 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 彼らの代表作のひとつとして挙げられる事の多い5作目。実際それは事実だと思います。それ故にクリムゾンを語る上では絶対に外せない作品なのですが、個人的に初心者にはどうも薦められない要素も多い気がするんですよね。70年代のクリムゾンにおいての特徴として歪んだギター、重たい雰囲気や高い緊張感が挙げられますが、この作品においてもそれは同様です。 そしてこのアルバム独自の特徴として『音にやたら隙間が多い』というのが挙げられます。それがこのアルバムを取っ付きにくいモノにしていると思うんです。とにかくすんなりと始まる曲が少なくて全体的に勿体つける作りの曲が多いのです。それがクリムゾンを初めて聴く人がどう思うかというのが問題でして。俺の場合は、それを考慮に入れた時にこの作品を一番最初に薦めるのはどうのなかと少しためらいが生まれたんです。というのも、俺が個人的にその音の隙間や勿体つける作りに最初はかなり難解な印象を受けたからなんですよね。 01『Lark' Tongues In Aspic Part1』がその特徴を象徴する曲で、本格的に曲が始まるまで3分以上もかかります。普段コンパクトな曲しか聴かないような人にとっては3分ってかなり長い時間ですよ。そこがまず障害となるんじゃないかしら。でもちょっと待って。じっくり聴いてくださいな。少しずつフェイドインしてくる序章とも言えるミューアによるパーカッションパートに戸惑う人もいるでしょうけど、曲が始まると凄まじい緊張感が押し寄せてきますから。激しい展開から中盤での妙な静のパートそして再び激しい展開、最後は静かに幕を閉じる複雑な曲構成はスリリングでカッコイイです。ライブでは06『Part2』の方が頻繁にプレイされるけどこれも凄い曲ですよ。 02『Book Of Saturday』は静の部分を強調した歌モノ。逆回転を利用したギターが使われていてちょっと凝った感じなんだけど個人的には並という印象の曲。決して悪くは無いけどね。03『Exiles』も01『Part1』同様なかなか始まらない曲です。これは凄く美しい歌モノ。02よりも美しさが際立っています。アコースティックギターが良い味付けをしていてとても好きです。 04『Easy Money』はサクっとはじまる。引きずるようなフリップのギターと低音がズシズシと大地を踏みしめるようなリズムで幕を開け、静のパートへ。この曲はミューアの控えめなパーカッションが絶妙な味付けをしているのが良いですね。フリップのギターソロは微妙にブルースがかっている気がするのが面白いけどなんとなく中途半端なのが残念。どうせならもっと濃ゆくやっちゃえば良かったのに。 05『The Talking Drum』は06『Part2』と殆ど繋がっていてライブでもこの2曲は続けて演奏される事が多いです。この曲も再びなかなか始まらないです。非常に直線的な構成の曲で徐々にフェイドインして音数も増えていき最後は緊張の糸が切れるかのようにキィィィ!と耳を突く音で崩壊しそのまま06へ続きます。この曲は単独ではあんまり意味をなさない気がしますね。06の壮大なイントロといったところで、そのイントロとしての機能は充分過ぎる程果たしていると思います。でも気が短い人は我慢出来ないかもね。 06『Part2』は非常に輪郭のハッキリしたわかり易い曲でライブでも定番曲。ギターが中心の曲で単純にカッコ良いです。ウェットンのベースも非常にセンスが良いですね。全体として各パートのアレンジがジャズっぽさよりもずっとロックらしさが前面に出た楽曲といえるのではないでしょうか。複雑にせわしなく各パートが絡み合う『Part1』よりずっとロック調の曲だと思います。このアルバムの中では一番分かり易い曲であり、目玉の曲の一つでしょうね。 ここまで読んでだいたい分かったと思うけど、この作品のとっつき難さの原因は音にやたら空間がある・・・というか平たく言えば『なかなか始まらない曲が多い』ので我慢強くない人はイントロでイライラしたりしそうって部分なのよ。だから超名盤にもかかわらず初心者オススメ度は控えめに星4つとしてみました。俺自身その『空間』に慣れるのにかなり時間がかかったんですよね。 【Personnel】-------------------- David Cross [Violin, Viola, Mellotron] Robert Fripp [Guitar, Mellotron & Devices] John Wetton [Bass & Vocals] Bill Bruford [Drums] Jamie Muir [Percussion & Allsorts] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
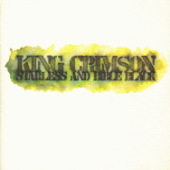 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| オリジナルアルバムとしは01、02、04を除いて全てライブ録音という特殊な6作目。 その元なったライブは現在では『The Night Watch(邦題:夜を支配した人々)』というライブ盤で聴く事が出来ます。伝説の公演と言われている73年アムステルダム公演からの録音です。その音源を元にスタジオでオーバーダブを施し完成となったのがこの作品というわけ。 このアルバムが発表された当初は収められている曲の半分以上がライブ録音であるという事実は不明で、それが明かされた時には誰もが驚いたようですね。実際、それを知りながら聴いても信じられない程完璧な演奏なんですよ。っていうか今でも信じられません。そして俺の中ではこのアルバムがクリムゾンの究極の形であり、誰がなんと言おうと彼らの最高傑作であると思っています。ここに収められた8曲全てが本当に恐ろしい程の完成度で、ロバート・フリップの頭脳の中にあるクリムゾンを動かすための歯車が全てかみ合った瞬間だと思ってしまう程の脅威の作品なんです。 スタジオ録音である01と02ではメタル的な要素を多く含みこのアルバムの入り口としは申し分ない勢いとキャッチーさを兼ね備えた楽曲に仕上がっています。特に01は非常に勢いがあり実にわかり易く一度聴けば確実に耳に焼きつくインパクトも備えています。難解な曲が多いこの作品ですが、入り口となる最初の2曲にこのようにかなり分かり易い曲を持ってきているのは素晴らしいですね。俺がこの作品にすんなり入れたのはそのせいかもしれません。 03,05,06,07はなんと全てインプロヴィゼイション。それなのにこれだけのモノが出来てしまうのには何か魔力のようなものが彼らに作用したのでしょうか。03は前述したようにインプロ曲なんですが、曲の序盤ではバラバラになっている曲のパーツ一つ一つを少しずつ拾い集め、そしてそれが組みあがり突如一体となって動き出すその展開に鳥肌がたちます。インプロ曲でありながら何か計算されているかのような絶妙なバランスに驚くばかり。05は03とは違うタイプのインプロで浮遊感のある美しい曲に仕上がっていますが、本当にインプロなのかと疑ってしまうようなまとまり具合です。事前にある程度相談して演奏してるのかなあ。そうじゃないとしたらマジで凄すぎるよ。 そしてなんと言ってもこのアルバムのハイライトは08の『Fracture』でしょうね。11分を超える大曲で、これも前述したライブでの録音ですが、これはインプロでは無くて、クレジットを見るとロバート・フリップ一人の作品となっています。最初から最後まで全く無駄な部分が無くギリギリまで引っ張った緊張感をその極限状態のまま最後まで保ってしまう脅威の作品です。とにかく全ての楽曲において素晴らしい緊張感が維持されていて聴き手を一度掴んだら最後まで離さないのです。 それまでインプロと計算された楽曲との同居を試みてきていた彼らの歯車が全て噛み合った瞬間がここにあります。しかし、インプロ曲の多さから初心者に薦めるとなるとちょっと無理があると思います。俺としてはファースト以上にクリムゾンの1つの世界観が実を結んだ瞬間を封じ込めた永遠の名作だと思っているんですけどね。なので、ある程度他の作品を聴いてからで良いので最終的にはこの作品にもぜひチャレンジしてもらいたいですね。 【Personnel】----------------- David Cross [Violin, Viola, Keyboards] Robert Fripp [Guitar, Mellotron & Devices] John Wetton [Bass and Voice] William Bruford [Percussives] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
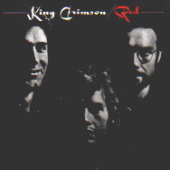 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 1974年にリリースされた70年代クリムゾンの最後の作品で通算7作目。この作品は解散が決定してから製作されたアルバムです。この作品は初心者オススメ度がダントツでナンバーワン。俺としては初心者にはまずこのアルバムを聴いてもらいたいと思います。 ヘヴィー・メタル色が非常に強く全体的にダークなイメージではあるのですが、難解な部分が少なく各楽曲の輪郭が非常にハッキリしている為に即効性が高いんですよ。何度も聴きこまなくてはいけないような忍耐力がかなり少なくて済む分かり易い作風。しかもダークなだけではなくキャッチーな要素もふんだんに盛り込まれているのでアルバムとしてのトータルバランスもかなり優れていると思います。ダークでヘヴィーという意味では2000年の『The ConstruKction Of Light』に通じる作風とも言えるのですが、前述したようにこちらの方が圧倒的にキャッチーで取っ付き易いです。ウェットンの歌のメロディーが素晴らしく歌とインストのバランスも初心者にとっては丁度良い具合になっていると思います。 01『Red』は80年代、90年代、2000年代と末永くライブで演奏され続ける事になるライブでの超定番曲です。ウェットンの歌の無いインストナンバーなのでこの作品中では最もダークな色合いだけど単純にカッコイイ曲ですね。02『FallinAngel』は一転してウェットンの歌が素晴らしい歌モノ。この曲はライブでは殆ど演奏されていない(というか全く?)のが残念でならない程名曲です。このメロディーはクリムゾンの歴史の中でも屈指の出来だと思うんだけどなあ。なんでライブでやんないのかな。『In The Court Of The Crimson King』の頃の美しさと、このアルバムでの破壊的な雰囲気の両方が混在している曲だと思います。 03『One More Red Nightmare』は緊張感溢れるイントロで勢いよく幕をあけるこの曲は01『Red』をキャッチーに仕上げつつ歌も軽快に乗せてみましたという雰囲気の曲。かなりわかり易くて好きな人にはすぐ好きだと言わせるだけの即効性がある曲。俺も大好きです。04『Providence』はライブボックスセット『The Great Deceiver - Live』のDisc1全曲とDisc2の初めの2曲で聴ける1974年6月30日ロード・アイランド州プロビデンスのパレス・シアターでのライブから。つまりこの曲だけライブ録音で、あとで手を加えて収録されています。ここでのバージョンは後半部分が少しカットされているけどフルバージョンは『TheGreat Deceiver - Live』で聴く事が出来ます。 この曲はインプロ曲なのでこのアルバムの中では最も難解な曲といえるでしょうが、インプロ曲としてはかなり分かり易く仕上がっている方だと思います。序盤こそ音がバラバラとフワフワと浮遊するようなつかみ所の無い構成だが後半からはリズムが刻まれ一体となって動きはじめるのでインプロを全て理解できる程のマニアではない僕にもインプロならではのカッコよさは充分伝わってきたし、初心者がはじめて触れるインプロとしては悪くないと思いますよ。 そしてラストはクリムゾン屈指の名曲『Starless』静と動のコンストラストを最大限に活かした超名曲。クリムゾンを聴くならばやはりこれを聴かなければ。前半部分は美しいメロディーをフューチャーしたパート。そのメロディーとアレンジは美しく、切なく、感動的です。中盤からはジックリと溜めて焦らして上で徐々に盛り上がっていくインストパートです。そこでの躍動感がまた素晴らしいです。キモはやっぱり後半のインスト部分ですね。 と、ここまで初心者初心者って書いてきたけど、単純にクリムゾンの歴史の中でも、ロックという大きな枠の中でもこの『Red』紛れも無く名盤であると断言しちゃって良いと思います。 【Personnel】------------------- 正規メンバー Robert Fripp [Guitar and Mellotron] John Wetton [Bass and Voice] William Bruford [Percussives] ゲストメンバー David Cross [Violin] Mel Collins [Soprano Saxphone] Ian McDonald [Alto Saxphone] Robin Miller [Oboe] Marc Charig [Cornet] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
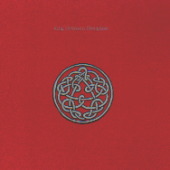 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 80年代に復活した通算8作目。80年代ではどれを最初に聴けば良いかしら? と訊ねられたらまあこの『Discipline』を薦めるのが妥当なセンだと思います。80年代に復活したクリムゾンは元々『Discipline』という別のバンドとして動き出したのですが、フリップが『これはクリムゾンである』と言い出したのを機にクリムゾンへと改名し以降80年代3部作が同じメンツで製作される事になりました。そんな経緯がある事からわかる通り70年代のクリムゾンとはかなり違います。僕はリアルタイムで彼らの変化を体験して来た人間ではないのでそれほどの驚きは無かったのですが、リアルタイムでクリムゾンを追っていた人がニューアルバムとしてこれを聴いたらやっぱり驚きますよね。 ブリューが持ち込んだポップ感覚、ポリリズムの多様、なんだかツルリとしたギターの音色とちょっと聴いただけでも全然違うのがハッキリわかります。かといって70年代との比較は今となってはもう無意味でしょうね。80年代のクリムゾンはこういうものだと割り切って接するしかないわけで。70年代のクリムゾンが良ければそれを聴けば良いんです。ただそれだけの事。だからこそ俺は80年代のクリムゾンにしかない魅力を見つけ出したいし、これを楽しめればそれはそれで素晴らしいことだと思いますけどどうでしょ。 このアルバムには以降のライブで積極的にプレイされる曲が沢山入っているし、現在ではこの時期のクリムゾンの作品中最もマニアにも評判が良い作品です。元々はそれまでの変化からかなり酷評されたようなんですが今となっては好意的な意見のほうが目立ちますね。それまでのクリムゾンには無かったサウンド作り故にポップス的なカラーを感じますが、実際は80年代3部作のなかでは最もポップ感は低く、スリリングな展開の曲が多いんですよ。それも評判が良い理由のひとつなんでしょう。 01『Elephant Talk』は話すようなブリューの歌が印象的でこれ以降こういうタイプの曲が結構存在しますが、その無表情な歌と短いリフの反復が不思議な緊迫感を生み出していて良い感じ。だけどこの曲に関しては個人的にはあんまり好きなじゃなかったり。こういう音作りなのならばポップ感がもっと強い方が好きなもんで。02『Frame By Frame』は楽器をやる人には魅力的であろう曲でポリリズムが非常に分かり易い形で取り上げられています。 ポリリズムってのは拍子がズレている二つの短いリフを同時に演奏しはじめて、元々拍子がズレているからそれを繰り返すことによってズレがドンドン大きくなっていき、ズレがひとまわりした結果、頭が再び揃うという手法のことです。自分が楽器を演奏しないような人はそういうのはよくわからないかもしれないけど、意識して聴いてみると『ああ!これのことか!』って面白さが増すかもしれないですよ。個人的にこの曲はその要素よりも歌メロがステキなので好きな曲なんですけどね。コーラスなんかもフューチャーされているのでなかなか壮大で歌モノとしても気持ちが良いんです。 03『Matte Kudasai』はそのものズバリ『待ってください』です。日本語なんですよ、これ。浮遊感のあるダル〜イバラード調の歌モノで、最初はあんまり好きじゃなかったのだけど何度も聴いていたら妙な味が出てきて好きになった曲ですね。しかしブリューの『まっつぇ〜くどぅぁさ〜い』は何度聴いても笑えるよ。やっぱし日本人が聴くと違和感あるよね。 04『Indiscipline』は気持ちが高揚するとてもとてもスリリングな曲。01『Elephant Talk』同様に話すようなブリューの歌が特徴的。だけどこちらの方が圧倒的に威圧感があって何度聴いてもドキドキするので僕としてはこっちの方が好きですね。夜一人で聴くとなんとなく怖くなるような緊迫感というのか。なんか知らんけどおっかないんだよな、この曲。歌詞の『I Repeat My When Under Stress』という部分をを繰り返し歌う部分があるのですけど、ライブではここが凄く強調されていてよく舌をかまないなと何度聴いても思います。一回ぐらいは噛んだことあるに違いない! 05『Thela Hum Ginjeet』はノリノリです。ウネルベースが非常にカッコイイですね。曲名は『Heat In The Jungle』のつづりを変えたものだそうです。演奏とノリは非常に好きなのですけど歌メロは猛烈にダサいです。そのダサさも何度も聴けば味になるとフォローしておきますけど。ライブでは非常に栄える曲ですね。でも歌メロは誰がなんと言おうとダサいです、ええ。04,05と緊張感がある曲が続いた後はギターシンセが鳴り響く06『The Sheltering Sky』で最もダルイ曲。これは要らなかったよなあ。ハッキリ言ってカッタるいです。ラストはタイトル曲である『Discipline』。とてもリズムが複雑な曲なんだけどあまり緊張感は感じられなくて割とテンションは低く、ギターの絡みを色々詰め込んでみましたという感じの曲。これもあんまり好きじゃないなあ。 冒頭でも述べたけど80年代を代表する作品であるのは間違い無いんですが、俺としてはポップ感が強い『Three Of A Perfect Pair』の方が好きなんですよね。因みに、俺が持っているこのアルバムは『30th Anniversary Edition』で、それは2001年に発売されたモノです。それ以前の『The Dedinitive Edition』では『待ってください』においてフリップのギターがカットされていたようなんですが、俺が持っている方ではそのカットされていないバージョンがボーナストラックとして収録されています。つまり現在CDショップに並んでいるこのアルバムのボーナストラック『待ってください』の方が実はオリジナルバージョンの『待ってください』なんです。意味わかります? 別に俺はマニアじゃないからどっちでも良いけどさ。 【Personnel】-------------------- Adrian Belew [Voice, Fretted and Fretless guitars] Robert Fripp [Guitar] Tony Levin [Bass, Stick, Synth and Background Voice] Bill Bruford [Acoustic and Electric Drumming] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
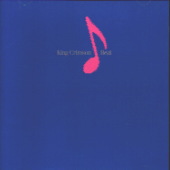 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 80年代クリムゾンの第二作で『Discipline』と同じメンツで製作されている通算9作目。同じメンツで続けて2つ以上の作品を作り上げたのは今回がはじめて。というか結局このあとの作品も同じメンツで作られ80年代は全て同じメンツで貫かれました。01『Neal
And Jack And Me』は前作と同じ流れをくんだ曲ですが、ポップなメロが個人的にはとても好きな曲ですね。 02『Heartbeat』は凄く普通っぽい曲でまるっきりポップスと言って差し支えないような曲。コード進行とかは全然普通じゃないんだけど、聴いていてヘンテコな曲って感じはしません。かなりシンプルでクリムゾンの曲なのに聴いていて『あれ?これで終わり?』って思っちゃう。でもメロディーは一回聴けば耳に焼きつくなかなか上質なモノだと思います。俺は凄く好きだな。 03『Sartori In Tangiers』はインスト曲で『それまでのクリムゾンらしさ』ってのが割と出てるとは思うけど、どうも中途半端な印象で盛り上がり切らないのが不満です。もうちょっと濃い曲に仕上げて欲しかったっすね。こういうインスト曲までもが淡白に作られている事からこのアルバム全体もやけに淡白に感じるのだと思います。基本はポップでも全然構わないから濃ゆい部分は濃ゆく作ってほしかったって思いますね。そうじゃなかったらこういう中途半端な曲は省いて徹底的にポップにするとかさ。その中途半端さがこのアルバムをつかみ所の無い作品にしちゃってる気がするんですよね。 04『Waiting Man』もアレンジから歌メロまで全てが中途半端。うむむむ。とてもつまらない曲。05『Neurotica』はこのアルバム中でもっとも緊張感のある曲で、同時にもっとも『らしい』曲でしょうね。80年代のクリムゾンでは話しているようなブリューのボーカルがフューチャーされている曲が結構あるけどこれもその中のひとつでその畳み掛けるような歌の乗せ方が緊張感を生み出しています。 06『Two Hands』は完全に歌主体の曲なのですが、メロがつまらないのでとても退屈。07『The Howler』は短い中で曲展開が激しくなっていてスリリングな曲だと思います。曲の展開は好きなんですが歌メロがなんだか中途半端なのが残念。とにかく4分に色々詰め込んでみました、という曲。ラスト『Requiem』はフリップのソロの為の曲という感じ。つまんねー。こういうのを最後に持ってくるとどうもアルバム全体に締まらない印象が残ってしまうし本当に必要ない曲じゃないかな。とにかくダルイです。 このアルバムは80年代クリムゾンの3部作の中でも最もシンプルで淡白な印象が強くて収録時間も35分ちょっととかなり短いので聴いた後に疲労感が全く伴わないです。だからこそ聴き易いと言えるのですが実際はそれよりも物足りなさ、中途半端さの方が強く印象に残ってしまうのが残念。俺は次作『Three Of A Perfect Pair』の方が好き。まあどちらも同じと言えば同じなのかもしれないけど次作の方が圧倒的にメロが魅力的で物足りなさはこの『Beat』程は感じないんですよね。メロをもうちょっと大事にして欲しかったなあ。 【Personnel】-------------------- Adrian Belew [Voice, Fretted and Fretless guitars] Robert Fripp [Guitar] Tony Levin [Bass, Stick, Synth and Background Voice] Bill Bruford [Acoustic and Electric Drumming] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
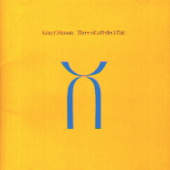 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 80年代のクリムゾン3作を結局同じメンバーで創りきったその最後の作品。通算10作目。前作『Beat』と同様にキツイ曲はキツイけど好きな曲も多くあるので、俺の場合は、古くからのクリムゾンファンに多い完全否定な評価にはならないです。むしろ高評価。だけどキツイ曲はキツイんですけどね。だから『Beat』とこの作品の好きな曲だけを集めて一つに編集したら文句の無い『変態ポップアルバムの名盤』になったんじゃないかなって思ってます。この作品ではそれまでとは違う形での『実験曲』が多く収められている印象で、その曲が総じてツライのが残念でならないです。 01『Three Of A Perfect Pair』は第六期と言われる2000年代のクリムゾンにおいてアコースティックバージョンとしてライブで演奏されています。この曲はかなり名曲だと思います。80年代のクリムゾンと曲はどれもこれも『クリムゾン的名曲』ではないのかもしれないしこの曲も同様なのでしょうけど、リアルタイムでこの作品と出会っていない俺にはそれはあまり関係のない事ですので、これはこれで素直に楽しめます。だから『クリムゾン的名曲』であるか否かはとりあえず置いておいてこの曲は単純に『ポップス的名曲』ですよ。僕にとっては前作『Beat』における『Neal And Jack And Me』や『Heartbeat』と同様の位置付けで、クリムゾン的か否かという問題以前にその曲が持つメロディーとポップ感が好きなんだから仕方ねえじゃねえかという曲ですね。 それと02『Model Man』、04『Man With An Open Heart』なども同様でして、単純にメロディーが好きですね。ここまで書いていて思ったんだけど、80年代のクリムゾンは歌モノとしての魅力を見出せる人ならかなり楽しめる要素が多いですよ。プログレというジャンル自体を愛好するファンに『ポップスに成り下がったか』という評価をされるのも当然だし気持ちも分かるけど、俺は良いメロディーさえあれば楽しめてしまう体質なのでこのアルバムの最初の2曲の流れや04なんかは全然退屈に感じないです。 とはいいつつ80年代のクリムゾンを今回レビューを書くにあたってまとめて聴きなおして改めて思ったんですが、やはりこれはクリムゾンではないんだろうし当初の予定通り『Discipline』というバンド名で活動していれば良かったんだろうな、とは思いますけど。そうすればここまで80年代クリムゾンが叩かれることはなかっただろうし、もっとメロディーの良さに注目する人もいたのではないかと思うと非常に残念ですね。03『Sleepless』では70年代クリムゾンぽさを感じる曲でライブでも結構演奏されています。03は、これはこれで好きです。 で、05、06、08は正直ツライです。70年代までのプログレッシヴな精神が形を変えて登場するというかなんというか。前衛的な事をやっているとは言えるのかもしれないけど、そこには70年代の頃の『前衛的でありながらも常に緊張感を保っていた』音ではなく、ただひたすらつかみ所の無い『音』がフワフワと浮遊しているのみ。この辺の曲を聴いていたら、ケミカルブラザーズとかのわかり易いテクノではなく、もっとヘンなテクノを好きな友人から聴かせて貰った『音楽になってない音』で構成されたテクノを思い出しました。そんなヘンテコ具合です。07『Dig Me』に関しては何故か好きです。充分わけわかんない曲なんですけど不思議と好きで理論的には説明不能ですね。好きなんだから好きなんじゃい。 そしてラストは09『Larks' Tongues Aspic Part3』。太陽と戦慄シリーズの復活。何故この曲名をこの曲に採用したのかはわからないけど、それでとても損をしている気がします。看板の重さということを指摘されて批判される事が多いようですが実際そんなのどっちでもいいです。このアルバムにおいて唯一クリムゾン的な緊張感を味わえる曲でなかなか悪くないと思うけどな。そりゃPart1やPart2に比べりゃ比にならないのかもしれないけど、これはこれで好き。ライブ盤『Absent Lovers』においてさらに魅力のある演奏が楽しめるのでそちらもぜひどうぞ。 総合して少し極端な評価かもしれないけどポップ好きの俺としてはクリムゾンに求められるものよりもメロディーの良さを重視して個人的には星は4つ。星ひとつ分は中間部のヘンなテクノみたいなところの減点分ですね。でもクリムゾンをこれから聴こうという人には間違っても薦められないので初心者オススメ度は星ひとつという事でいかがなもんでしょ。最初に書いたけど『Beat』とこの作品の好きな曲だけを抽出したら絶対僕的名盤になったと思うので、今度自分でその2作品を一つにしたベストを作ろうかと思います。 【Personnel】-------------------- Adrian Belew [Voice, Fretted and Fretless guitars] Robert Fripp [Guitar] Tony Levin [Bass, Stick, Synth and Background Voice] Bill Bruford [Acoustic and Electric Drumming] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
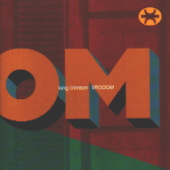 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| ダブルトリオとなった第五期クリムゾンの最初の作品で、次作『Thrak』の予告編的なミニアルバム。通算では11枚目。ギター、ベース、ドラムが二人ずついるという思い切った編成で、それを活かしたような曲を作ろうとしているのが聴いて取れます。ダブルトリオの利点をフルに活かしきれていない曲も当然あるけど、それを指摘するのは酷でしょう。別に常に6人がギチギチに演奏していなくてはならないなんて事は全く無いんだから。 で、これはたった4日間でレコーディングされ2週間の間にミックスが完了したという本編に先駆けた『とりあえず』的なアルバムなので軽視さえてしまいそうだけどちょっとまってよ。俺は充分気に入っているアルバムなんですよ。凄く良いと思うんだけどな。俺は『Thrak』の作りこまれた録音と演奏よりもこちらのラフさの残る録音と演奏の方が好きなんですよね。80年代クリムゾンのような軽い感じはここにはなく非常に重たい音となっていて非常にメタル色が強いです。それ故に、このくらいのラフさの残る録音と演奏の方が楽曲がライブ感を発して魅力が増すような気がするんですけども。まあ結局は好みの問題ですけど。 この作品はヘヴィーである反面、意外とキャッチーで楽曲がコンパクトにまとまっています。ポップスっぽかった80年代と比べても明らかにロックな音となっているので最近のロックファンにはかなり聴き易いのではないかと思います。しかも6曲で30分強と気楽に聴ける感じも初心者には良いですね。次作の『Thrak』と被る曲も多くあるけど(といってももちろん別テイクですけど)、03『Cage』、05『When I Say Stop, Continue』は『Thrak』には収録されていない曲です。 01『Vroom』は正にメタルクリムゾンと言うべき曲。『Red』の頃のクリムゾンを思い出します。これは本当にわかり易い曲なのでアルバムの幕開けの曲としては充分に魅力のある曲でしょう。02『Sex Sleep Eat Drink Dream』は歌を中心にした曲で、妖しさ充分のクリムゾンらしさを感じつつも非常に聴き易い曲。後半部分はヘヴィーに盛り上がり『Vroom』同様メタル色が強いので個人的にはかなり好きな曲ですね。 03『Cage』は間つなぎ的な1分半しかない短い曲だけど駆け抜けていくようなノリの良さはなかなかカッコイイです。まだ固まりきれていない状態でとりあえず入れたという印象なのが残念です。もっと煮詰めれば立派な楽曲になったんじゃないかしらね。04『Thrak』はインプロ曲と事前に作られた楽曲の中間の雰囲気を持った曲でこのアルバム中でもっとも『濃い』曲。ダブルトリオならではの音数の多さや各楽器の絡みが威圧感を生み出し相当聴き応えのある楽曲に仕上がっています。 05『When I Say Stop, Continue』はいらなかった気が。クリムゾンのインプロ的な曲の中でも嫌いなタイプの曲です。基本的にリズムが無くてただバラバラに各楽器がのたうち回るだけ。最後は一応一丸となって突進してくる雰囲気を出しているけど全然中途半端でイマイチだな。この曲がなければアルバム全体を一気に聴ける爽快感があったのに流れを断ち切ってしまっていて勿体無いです。なんかヤケクソ?って感じの曲ですね。最後の06『One Time』はシットリとした歌がメインの曲でこのアルバム中でもっともポップス寄りの雰囲気。ちょっと洒落た感じですね。俺は好きです。 以上のように全体としては比較的聴き易い『ロック』な作品に仕上がっているので、60年代や70年代の古い録音の作品を聴きなれていないような若い層の入り口として非常に手軽でとっつき易い作品といえるのではないでしょうか。 【Personnel】-------------------- Robert Fripp [Guitar] Adrian Belew [Guitar, voice, words] Trey Gunn [Stick] Tony Levin [Basses and Stick] Pat Mastelotto [Acoustic and Electronic percussions] Bill Bruford [Acoustic and electronic percussions] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 通算12作目。前作『Vrooom』の本体となるフルアルバムで前作より遥かに作りこまれた演奏と録音です。けど個人的にはなんだか少しこじんまりしている印象を受けてしまいました。かといってキライって意味じゃないですけどね。むしろかなり傑作だと思っています。でもこれがもっと前作のようなラフな録音だったら、よりロックっぽく単純にライブ感が出たんじゃないかなというだけの事です。なので大きなマイナス要素としては認識していません。 この作品ではダブルトリオの特性を活かそうという心意気は前作以上のようですね。どうやらダブルトリオの特性をアピールする為なのかステレオの左右をかなり分離させて強調している部分があります。それは01『Vroom』。そりゃステレオなんだからそういう風に分かれるのが普通だろとか言われそうだけど、他の曲と比べて明らかに聴こえ方が違うのよ。ヘッドフォンで聴いてみると凄く分かり易いので試しに聴いてみて頂戴な。 で、その01『Vroom』は前作の再録版。前作では02『Coda:Marine475』と繋がって一曲になっていたんだけど今回は何故か二曲に分離して収録しています。あんまり意味が無いと思うんだけどなあ。03『Dinosaur』はシングルになった曲で力強いブリューの歌がカッコイイです。ブリューって下手下手言われてるけどそーかなあ。俺は普通に巧いと思うけど。ウェットンは褒められる事が多いようだけど俺にはそんなに違いがわかんないです。耳が悪いのかしら。 04『Walking On Air』は素晴らしいヴォーカル曲だと思います。メロディーが秀逸。クリムゾンに求められるようなタイプの曲ではないのかもしれないけどメロディーの良さは相当なものだと思いますよ。05『B' Boom』はダブルドラムのバトルといった感じでなかなか緊張感のある演奏が展開されています。そしてその05は06『Thrak』のイントロ的な曲になっていて2曲で1組といった感じ。繋がり方もかなりカッコイイのでベストなんかを作るんだったらこの二曲はくっつけないとね。 07は繋ぎの曲で全然意味ナシ。こういうのを入れるってのは実際理解に苦しみます。12も同様な曲で無駄に曲数を増やしてるだけだしもっと要らないのは09『Radio』と11『RadioII』。完全にただのSE。こんなの曲としてわけないでいいってば。08『Poeple』はファンキーな感じでとてもリズムカルな曲。こういうノリってクリムゾンじゃ珍しいですね。俺はリズムが中心となった曲はとても好きな方なので素直にただカッコイイと思いました。10『One Time』は前作『Vrooom』に入っていた曲の再録。前作とあんまり印象は変わらないかな。 13『Sex Sleep Eat Drink Dream』も同様に再録。この曲は『Thrak』バージョンの方がキレが良くて、よりカッコイイ曲となっています。良い感じに生まれ変わったと思うな。14『Vroom Vroom』は01『Vroom』の別解釈の曲という感じで『Vroom』よりもさらに『Red』を連想させます。というか展開も『Red』と似てるしね。とてもメタルな曲。そしてラストは14『Vroom Vroom』のCodaであり、それと同時にこのアルバムを締めくくるCodaでもあるという曲。これもメタルですね。メタルというか引きずるように重たいギターはむしろラウドロックを連想させる程。単純にカッコイイよ。 このアルバムは前作と同様に若い層へのクリムゾンの入り口に成りうる貴重な佳作だと思います。メタル色が増したダブルトリオでの第五期クリムゾンはたった2作で幕を閉じる事となったのが残念です。こういうテイストのアルバムをまだ何枚か聴いてみたかった気がします。 【Personnel】-------------------- Robert Fripp [Guitar, Soundscapes, Mellotron] Adrian Belew [Guitar, Voice, Words] Trey Gunn [Stick, Backing Vocals] Tony Levin [Upright & Electric Basses, Backing Vocals] Pat Mastelotto [Acoustic & Electronic Percussions] Bill Bruford [Acoustic & Electronic Percussions] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
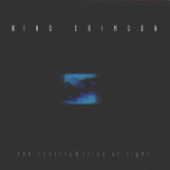 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 通算13作目。新生クリムゾンへ向けての実験プロジェクトシリーズを経て発表された2000年代クリムゾンのアルバムです。徹底してダークで重い作風。ヘヴィーという点を考慮に入れれば90年代の『Vrooom』や『Thrak』と共通するといえるのですが、90年代のクリムゾンの方がずっとキャッチーで表情豊かでした。 とにかくこのアルバムは愛想が良くないんです。聴く者を突き離しながら何故か自分から突進してくるような感覚です。そう正に突進。気を抜くような場面がなくて最初から最後まで強引に突進してくる感じ。だけど意外と聴き易いと思いました。リズムは複雑なのだろうし曲調もダークで無愛想なのにカラーが完全に統一されていて音に隙間があまり無いので逆に音を一つ一つ拾いながら聴く必要がないからかもしれません。放っておいても勝手に強引に耳になだれ込んでくるっていうかね。 そしてすぐわかる特徴はそれ以外にもVドラムの導入が挙げられます。いわゆる電子ドラム。生ドラムの持っている、ある程度ムラの存在する生っぽい響きではなく完全に制御された独特の音色の楽器です。これがかなり曲者で好き嫌いが分かれそうなんですよね。因みに僕もはじめはかなり気になりました。だけど何度も聴くうちに慣れてしまいました。とはいえ好きになったわけではなく、どちらかと言えばやはり生のスネアの音が恋しいのが本音ですけど。Vドラムの導入はすげえ微妙なんですよね、俺としては。 01『ProzaKc Blues』はダークなヘヴィーメタルのような曲でヴォーカルまでヘヴィーメタルのような印象。歌っているのはブリューなんですけど思いっきり加工してあって別人のようなひく〜い声に大変身しています。ヴォーカルのクレジットを見ると他の人物の名前が書いてあるのですけどそれは架空の人物で歌っているのは間違い無くブリューですので騙されないように。 02〜03は2曲で一対の『The ConstruKction Of Light』。前半部分にあたる02はインスト部分で、CDプレイヤーのトラック表示が03に変わるところからヴォーカルが被さるという構成。わざわざトラックナンバーを分けなくても良かったのでは? 曲は80年代クリムゾンの延長線上にある曲だけど、ポップ感は薄くて雰囲気は暗いです。04『Into The Frying Pan』は単純にカッコいいロックソングとして気に入っています。普段ヘヴィーロックや最近の重いメタルを聴く人にはすぐ魅力を見出せる曲である反面、濃いクリムゾンファンにはつまらない曲に思えるかもしれないですね。結構ストレートな曲だから。けど俺は好きです。非常に攻撃的でヘヴィーなのが分かりやすくて良いです。 05『FraKctured』は元々『Larks' Tongues In Aspic Part5』として創られた曲なんですが『Starless And Bible Black』収録の『Fracture』に似ているという指摘から改名されたとの事です。その辺聴き比べてみるのも面白いですね。中間部からのギターの荒れ狂い方が凄い。フリップさん大張きりって感じです。06『The World's My Oyster Soup Kitchen Floor Wax Museum』はエフェクトが掛かったダークな歌モノ。正に現代的と言える曲でヘヴィーロックという言葉を使いたくなるような曲に仕上がっています。ものすごい威圧感です。戦車で町を破壊しながら突進しているかのよう。俺は大好きです。 07〜09はひとまとまりで『Larks' Tongues In Aspic Part4』。この曲もダークで大迫力。破綻寸前のギターソロがのたうち回る様が壮絶で、そのバックは各パートが一丸となって迫ってきます。Part1のような劇的な展開はあまり見られずに、はじめから最後まで同様のトーンで貫かれているのでPart1のような『緊迫感』とは違う『威圧感』が前面に出た曲といえるでしょう。10『Coda:I Have A Dream』は完璧に09までの流れと繋がっているので、この10も合わせて『Part4』と言っても問題はないと思います。07〜09までの流れはそのまま引き継ぎながらもラストを飾るに相応しい壮大感とメロウな感じが同居した佳曲。ただのエンディングの曲として片付けるには勿体ないですよ、これは。 一応ここまでがクリムゾン名義での作品。ここまでで本編は一回終わって再びボーナストラック的な存在として11『HeavenAnd Earth』が始まる感じ。リハーサルでのインプロが元となっている曲で『ProjeKct X』名義での作品となっています。このアルバムの後に『ProjeKct X』名義でのアルバムが発表されているので、その予告編といったところなのだろうけどこういう中途半端な入れ方はしないで欲しかったなあ。やっぱり07〜10の素晴らしい流れで幕を閉じた方がアルバムとしての統制はずっと良かったと思うのですけど。まあ、この曲はこの曲で嫌いじゃないんだけどね。 このアルバムのダークな雰囲気から取っ付きにくさを感じる人もいるのかもしれないけど、ヘヴィーロックやヘヴィーメタルをよく聴く俺にとっては逆に聴き易い作品に思えましたね。なので普段そういう音楽を聴きなれている人の入り口としてあえて初心者オススメ度は星4つという思い切った評価にしてみました。ダークなのが好きじゃない人はそこから星を2つほど減らす感じでどうでしょうか。 【Pearsonnel】-------------------- Adrian Belew [Guitar and Vocals] Robert Fripp [Guitar] Trey Gunn [Bass Touch Guitar,Baritone Guitar] Pat Mastelotto [Drumming] [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
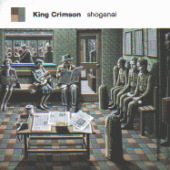  |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 次作『The Power To Believe』の予告編的な作品。曲数をみるとフルアルバムのようだけど実際は赤文字で示したモノだけがしっかりとした楽曲として成り立っている曲で他は全てわけのわからない中間曲。ジャケットの方にもわかり易く色分けして表記されています。なのでこれはフルではなくミニアルバムですね。90年代のフルアルバム『Thrak』に対する『VROOOM』のようなもんでしょう。 中間曲に関してはどれも短いんであっても無くても良いです。いや、無くていいや。こういう曲に魅力を見出せるほど深い感性は持ってないよ。どういう意図でここまで沢山の中間曲が収録されているのか俺には全く理解不能です。さらにまともな曲が4曲しかないのにその内の一曲がナッシュビルでのライブからの『Larks' Tongues In Aspic Pt.IV』。『ConstruKction Of Light』に収録されていた曲のライブバージョンです。これも良くわからないね。演奏の出来はとてもヘヴィーで良いものであると思うけど、ここに入れる理由がわからん。 となると聴き所は他の三曲#02、#05、#08ということになるわけだけど、タイトル曲の#02『Happy With What You Have To Be Happy With』はヘヴィー・ロックで『ConstruKction Of Light』からのカラーをそのまま引き継いだ曲。だけど結構キャッチーで『ConstruKction Of Light』の音像よりもスッキリしてるので非常に聴きやすく、逆に言うとインパクトには欠けます。でも単純にカッコイイ曲。次作『The Power To Believe』にも本作と同じ録音で編集が異なるモノが収録されましたが本作のバージョンのほうが1分ほど曲が長くなっています。 #08『Potato Pie』はなんとブルーズ風の曲。ハッキリ言ってダサい。というか、本人たちがどれだけマジでこの曲をレコーディングしたのかも謎ですね。彼らなりのジョークなのでは?と思える曲です。だから俺はそんなにまじめに捉えていないな。 #05『Eyes Wide Open』は透明感のあるヴォーカル曲で90年代における彼らのヴォーカル曲の流れを引き継いだ感じもの。フルアルバムにこの曲が入っていればアルバム全体のちょっとした表情付けの曲になって良さそうだけど、ただでさえ中間曲が多くて隙間だらけの本作にこんな感じの曲が入っていてもそれほど栄えないね。それなりに良い曲で好きだけどね。で、本作でのこの曲はアコースティックバージョンという注釈がついてますが次作に収録されることになる正規バージョンもそれほど印象に変わりなしです。 とまあそんな内容なので非常に中途ハンパなのですよ本作は。タイトル曲の#02は単純にカッコイイ曲だけど、アルバムというひとまとまりの作品として捉えた場合は隙間だらけのスカスカな内容。次作へ続く予告編という以外に特に特筆する部分はないな。あまりにも無節操にこういうものをリリースするのはちょっと理解に苦しむなあ。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| もう色んなライブ盤やらなにやらが常にリリースされまくりのKing Crimsonの2003年発表のアルバム(あまりにも色々出すぎてて『オリジナルアルバムの何th』とかいう言い方が出来んっ)です。本作の予告っぽいライブ盤『Level
Five』、さらにこれまた本作の予告編っぽい『Shoganai : Happy With What You
Have To Be Happy With』の二作を経てようやく正式なフルアルバムである本作がリリースされました。『ConstruKction
Of Light』の次の正式な『オリジナルアルバム』ってことでいいのかな。 90年代以降のKing Crimsonはやたらと新作を出すまでにアルバム完成までの途中経過を収録したような予告編的な作品を何度もリリースするようになってて、短いスパンでリリースされた作品同士で同じ曲が被りまくったりしてます。それぞれライブ録音だったり、バージョン違いだったりするんで、全く同じものを複数の作品に収めてるわけではないんだけど、ちょっとしつこいと思うよなさすがに。 本作ももちろん例外でなく前作『Shoganai : Happy With What You Have To Be Happy With 』(名前なげえ)やその前のライブ盤『Level Five』に入っていた曲と被ってたりしますが、その辺のことはとりあえず置いておいて本作の単独のアルバムとしての印象は至極良いです。『Level Five』に収録されていた#08『Dangerous Curves』は、最初は退屈に思えたんですが、本作の完成バージョンをフルアルバムの流れの中にで聴くと凄く楽しめましたし、そのライブ盤のタイトル曲『Level Five』も本作においては非常に良い感じでレコーディングされています。11曲で50分チョイってのも気楽に聴ける長さで良いです。 2000年の作品である『ConstruKction Of Light』と作風が共通する部分があってヘヴィー・ロックなテイストはそのまま引き継がれています。#09『Happy With What You Have To Be Happy With』もヘヴィー・ロック風で、ハッキリいってプログレという言葉で表すのにはかなり違和感を感じるほどわかりやすい曲です。彼らは確実に若いバンドの影響を受けています。 同曲は前作『Happy With What You Have To Be Happy With』にタイトル曲として収録されていた録音と同一のものの別ミックスバージョンでこちらでは曲が1分ほど短くなり音の印象もスマートになっています。終始ゴリ押しで非常に濃かった『ConstruKction Of Light』と違って聴きやすさを重視した形でアルバムにまとめるというのが本作のコンセプトなのかもしれませんね。さらにメロディーを前面に出した曲もあり、さらには#07『The Power To Believe II』では『KID A』におけるRadiohead的な雰囲気も感じます。 つまり一貫して同じカラーで統一されていた『ConstruKction Of Light』に対して本作はかなりバラエティーにとんだ内容で、息抜き出来る曲があったり勢いのある曲があったりするので聴いていて疲れないのが大きなポイント。一枚のアルバムで様々な表情を魅せてくれます。しかも、色々なことをやり過ぎて『聴き手置いてきぼり』になってしまうようなことも全く無く、楽曲がそれぞれ『良い曲』に綺麗にまとまっているのも良いな。これはプログレ好き以外にもとっつきの良い名作かも。 その代わりプログレバンドとしての新鮮味はないけどね。もっと言えばちょっと綺麗にまとまりすぎて良くも悪くもコンパクトな印象なのです。だから、そこを聴きやすくて良いと捉えるか、こじんまりしてしまったと捉えるかで大きく評価が分かれる作品でしょう。俺は本作には大きな新鮮味はないけど聴きやすくて素晴らしい出来のアルバムだと思います。凄く好き。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
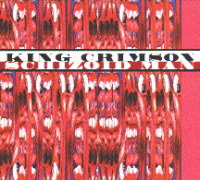 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| なんとなく笑ってしまった企画盤。同じ曲のバージョン違いが5曲入ってるって凄いですよ。タダでさえ濃い曲が、やっと終わったと思ったらすぐに再び『デ〜デレレ〜デッテ〜』って始まるのが5回繰り返されるんですからね。とは言うものの03〜05の違うライブの演奏を連続して聴き比べる事が出来るので楽しい企画盤ではあると思いますが、所詮はマニア向けということで内容についてあんまりクドクド書いても仕方ないですね。なのでこの作品のリリースの経緯を簡単に書いて終わりにします。 この企画盤は元々はイギリスで1996年にリリースされていたのですが、車のTVCMでこの曲が使われたのをキッカケに日本でもかなり遅れてリリースされたというモノです。日本ではCMに使用されたついでにちょっとでも売れればいいかなって感じで売り出されたんでしょうね。04,05はライブ音源としては貴重なモノだそうだけどこの曲のこの時代のライブバージョンは既に沢山出回っているわけで、俺は別にどっちでも良いけど。まあ、この作品は全部持ってないと気がすまないような人が趣味でどうぞって感じで。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
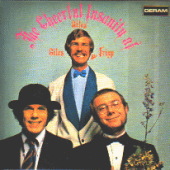 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 準備中 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■ALBUM [XXXX] | ||
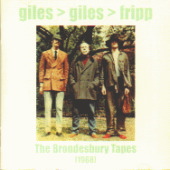 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 準備中 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| BACK |