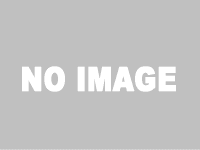| STEELY DAN |
DETAILS >>
|
|
ORIGINAL STUDIO ALBUMS ■CAN'T BUY A THRILL [1972] ■COUNTDOWN TO ECSTASY [1973] ■PRETZEL LOGIC [1974] ■KATY LIES [1975] ■THE ROYAL SCAM [1976] ■AJA [1977] ■GAUCHO [1980] ■TWO AGAINST NATURE [2000] |
| ■CAN'T BUY A THRILL [1972] | ||
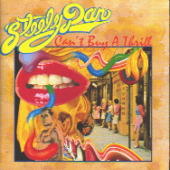 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| Steely Danの記念すべきデビューアルバムです。ドナルド・フェイゲンの癖のあるヴォーカルはSteely
Danの看板となっていますが、この作品ではフェイゲン以外にもヴォーカルをとる人がいます。デイヴィッド・パーマーがその人。それに加えてドラマーのジム・ホッダーも一曲リード・ヴォーカルを取っています。元々フェイゲンはリード・ヴォーカルを取る事を非常にイヤがっていたという話があります。結果的にこの作品においてはフェイゲンがヴォーカルを取っているのは半分程度の楽曲になっています。セカンドアルバムでは既にフェイゲンが全ての楽曲でリード・ヴォーカルをとる事になりましたが、それもはじめはかなり渋々だったそうです。 この作品でのSteely Danはドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーのプロジェクトという存在ではなく、まだ『バンド』としての存在となっています。といっても100%ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーのペンによる楽曲で構成されているので、後にSteely Danが二人のプロジェクト化するのはこの頃から殆ど決まっていたようなものなのかもしれませんね。 作風は彼らの作品中比較的ロック色が強いモノとなっていますが、だからといって荒々しいとかラフであるという表現は必ずしも正しくないと思います。この時点で既に充分洗練された音楽を創っていることに驚きを隠せません。楽曲のレベルは非常に高いです。後のSteely Danと比べるとかなり作風に違いがあるのは間違い無いのですが、少なくともここには既に青臭さはありません。デビュー・アルバムでこれだけのモノを創れるというのはやはり驚きですよ。ロック色が強いと言ってもジャズからの影響も充分に発揮していて後のSteely Danらしさも感じられる作品ですね。 フェイゲンの癖のあるヴォーカルが収録曲の半分程度ということでかなり『普通』な印象を受ける曲が多いように思います。しかしそれと同時にそれらは聴きやすい『非常に良い曲』でもあるのがポイントでしょう。デイビッド・パーマーが歌う02『DirtyWork』やジム・ホッダーが歌う04『Midnite Cruiser』は後のSteelyDanからはかなり離れた位置にある楽曲だとは思いますが本当に良い曲です。フェイゲンの歌が苦手な人はむしろこのアルバムの目玉になる曲とも言えるんじゃないかな。ただジム・ホッダーの声は物凄くドンくさいのでそれはそれで好みが分かれるかもしれませんけど。 この作品はデビューアルバムにしていきなりゴールド・ディスクを獲得しています。01『Do It Again』は全米6位、06『Reelin' In The Years』は全米11位を獲得しています。その06『Reelin' In The Years』ではエリオット・ランドールのロック色の強いギターが大活躍します。ロック畑の人の耳を一番引くのがこの曲であるのは間違い無いでしょう。 ジャズ、ロック、ファンクなど様々な音楽をSteely Danというフィルターを通して見事に具体化された作品であると同時に、その中でロックのカラーも充分に感じられる作品なのでロック畑の人がSteely Danにはじめて触れる場合は意外とこの作品が入り口になるかもしれません。初心者オススメ度は星を3つにしましたが、ロック好きの人の場合は初心者オススメ度は星を一つ足して4つってな感じでどうでしょう とにかくデビュー・アルバムからこの完成度とは凄い。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■COUNTDOWN TO ECSTASY [1973] | ||
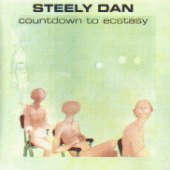 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| バンド形態にも関わらずバンドの正式メンバー以外に15人ものゲストミュージシャンを起用して製作されたセカンドアルバムです。この時点でフェイゲンとベッカーは既にバンドという狭い枠で作品を創る事には関心が無かったのでしょうね。二人の頭の中にある構想を作品として具体化する事を最重要視しはじめた結果なのでしょう。 この作品はダラっとした印象を受けてしまう人もいるかもしれないです。前作のような小粒に綺麗にまとまった感触はあまりなく冗長な感触。そういう意味ではよりジャズ的な解釈が強まったポップという感じでしょうか。特に04『Your Boston Rag』などはかなりジャズ色が強いです。 そんなインプロヴィゼイション的な印象の演奏(実際にインプロであるかどうかは別として)がこの作品の大きな魅力であり、逆にそういうのが苦手な人にはかったるい作品かもしれません。なので全体として即効性はあまり高くない作品なのですが聴けば聴くほど味が出る作品だと思います。 しかし、全てがジャズ的なわけでもなく、06『My Old School』のような愛嬌のあるポップソングや、『Pearl Of The Quarter』のようなカントリー風味の和やかな曲も顔を出します。特に『My Old School』は本当にノリのよいポップソングで個人的には大好きですね。『Pearl Of The Quarter』も地味な曲ではありますが味わい深くて好きです。 他には単調な繰り返しが5分間続く05『Show Biz Kid』は印象的な女性コーラスを大々的にフューチャーしていてなかなか面白い曲に仕上がっていると思いますし、08『King Of The World』はファンクっぽい16ビートと地味ながらよく聴くとかなり凝ったギターアレンジがなされていて味わい深い曲だと思います。全体の印象として最初は地味な印象を受けてしまって、僕がこの作品を手に取る回数はかなりすくなかったのですが、今となっては非常に聴き所も多い作品だと思っています。 彼らを代表する作品では無いにしても、ハイ・クオリティーな作品と言えます。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■PRETZEL LOGIC [1974] | ||
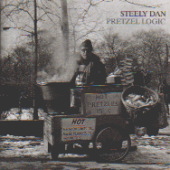 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 彼らの最大のヒット曲となった01『Rikki Don't Lose That
Number』を含むこの作品はアルバムとしての評価はファンの間では意外と評価が分かれる作品のようです。まず俺個人の評価を述べておくとかなり好きな作品。 前作はジャズ色が強い曲も多く含む作風で聴きこむことで味が出るような感じだったのに対し、この作品は逆にポップ色が強く、小粒な小曲集という印象が評価を分けている要因のようですね。それでもフェイゲンの癖のあるヴォーカルによって何処から聴いてもSteely Danという風に言えるのですが、彼らの作品の中ではかなりサラっとスッキリした淡白な作品であるのは確か。人によっては引っかかるモノが少ないのだろうなっていうのを感じる部分はあるね(俺は違うけど)。 逆に言えば特に聴きやすいアルバムなの。その『当り障りの無さ』を心地よく思うか、淡白だと思うかによってかなり感想が違ってくる作品と言えるでしょう。俺としては全体にアコースティカルなアレンジが心地よくて、ピアノやアコギがとてもサワヤカで非常に好きだね。その『当り障りの無さ』を俺は凄く気に入っていてBGMとしても邪魔にならない心地よさがありつつ、ふと意識を向けるとしっかり良いメロディーが耳に残るのが良いのよ。 先ほども書いたようにSteely Dan最大のヒット曲である01『Rikki Don't Lose That Number』で聴かれる美しく心地の良いピアノのアレンジや親しみやすいメロディーはそれ以外の曲にも共通していて、例えば04『BarryTown』なんかは本当に親しみやすいポップスに仕上がっていてとても素晴らしい。そんなポップス小曲集であるこの作品ですが、彼らの歴史の中でも唯一となるカヴァー曲『East ST Louis Toodle-Oo』なんかも入っていて面白いね。原曲はデューク・エリントンという人の曲だそうです。 本作で一際ポップで好きな曲が他のファンの間では捨て曲扱いされていたりする事もあるのがちょっと切なかったりもするけど俺は充分良い作品だと思っています。当り障りの無いポップも好んで聴くような人にはオススメの作品だね。 因みに『Rikki Don't Lose That Number』のイントロはHorace Silverの『Song For My Father』という曲のパクリだそうで、かなりそのまま流量されているらしいけどその元ネタを知らないので、俺はなんともいえないな。ファンの間ではその辺はとっくに承知の事実のようけどあんまり気にしてる人はいないみたい。それについてはもうちょっとああだこうだという人がいても良さそうなもんだけどチョット不思議なきもするなあ。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■KATY LIES [1975] | ||
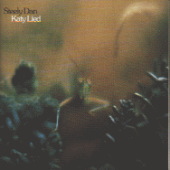 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 他のサイトのレビューを見る前に俺個人としても感じた事で、結果的に他のファンの人達と完全に意見が一致した部分がこの作品にはあります。それは『フェイゲンの歌の癖がやたら強い』ということ。本当にネバっこくてくどい歌いまわしが印象に残る作品です。02『Bad
Sneakers』、03『Rose Darling』、04『Daddy Don't Live In That New York City No
More』あたりのくどさは相当なものだよ。特にブルーズ色の濃い04においてはかなりクドイ。でも俺は04がこのアルバムで一番好きな曲。 楽曲自体の作りが前作に近い印象の割りとポップでサワヤカな曲が多いけど、そういった曲ではそのフェイゲンのネバっこい歌とのギャップが非常に面白い作品となっています。01『Black Friday』は軽快で割と爽やかな曲でこの曲においてはそれ程歌のくどさは発揮されていないんだけど先ほど挙げた『Rose Darling』は『曲調は爽やかなのに歌だけくどい』という曲の一つでとても面白いよ。 06『Eveyone's Gone To The Movies』は愛嬌のあるポップソングで演奏はとても可愛らしい雰囲気を醸し出していて凄く好き。でもやっぱりフェイゲンの歌が素晴らしくクドい。サビでは凄く爽やかに歌い上げるのだけど、そこに至るまでの歌はかなり面白いものとなっています。07『Your Gold Teeth II』はジャズ色が強い曲でかなり起伏の激しい曲。ポップで淡白に終始していた前作との決定的な違いを出している曲でしょう。インストパートにかなり聴き所が多い曲だね。08『Chain Lightning』はブルージな曲。この曲のフェイゲンはこのアルバムの曲の中ではかなりサラっと歌っている方ですね。 ポップな側面が強調された前作の流れの中にありつつもかなりバラエティーに富んだ作品となっているのが本作です。サラっと聴いただけだとフェイゲンの歌の濃さ以外はかなり地味な印象を受けるかもしれないけど、しっかり聴くと実はかなり内容の充実したバラエティー豊かな作品であることに気づく。フェイゲンのクドさがダメな人は徹底的にダメかもしれないけど、彼のクドさを楽しめる人にはなかなかの傑作ということになるのではないかな。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■THE ROYAL SCAM [1976] | ||
 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| 俺が彼らの最高傑作と名高い『Aja』に勝るとも劣らない大傑作だと思うのがこの作品。ロック色、ジャズ色、ファンク色などのそれまでSteely
Danが取り入れてきたそれぞれの要素が全て同じ位ずつ融合されたとてもバランスの良い作品です。Steely
Danのアルバムを聴くときにCDラックを眺めていて思わず手に取ってしまう回数が多いのは間違い無くこの作品だな。ポップ色が強かった『Pretzel
Logic』のポップ感も感じさせつつも基本的にかなり力強い作風で、はじめて聴いたときの即効性も相当高かったのもポイントのひとつ。 この作品はシングルヒットには恵まれなかった上にアメリカでのアルバムチャートにおいても最高25位という彼らの作品(2000年のアルバムは別にしてGauchoまでで)としては一番売上が低いからなのか、代表作のような言われ方をする事は殆ど無いようだけど、俺はこのアルバムは『Aja』と並ぶ傑作だと思っています。売れたから良い作品、もしくは売れなかったからダメな作品なんて事はないというのを改めて感じさせてくれる作品ですね。 01『Kid Charlemagne』は彼らの作品の中でも屈指の出来。とにかく単純にカッコイイ曲です。ラリー・カールトンによる流れるようなギターやファンキーな躍動感溢れるリズムが最高に気持ち良い曲。これを聴かずしてSteely Danは語れないと思う程好きな曲だよ。この曲は俺がSteely Danのアルバムを本格的に聴くキッカケにもなった曲なので非常に個人的思い入れが深いね。02『The Caves Of Altamira』もまた素晴らしい出来。この曲はポップ色が濃く出ている曲だと思います。サビへのメロディーの持って行き方が素晴らしい。 ピアノ、ギターなどの力強いプレイをはじめとして、最高に噛み合っているリズムセッションがこの作品を活き活きしたものにしています。各楽器のプレイはどれも最高のモノだと思うけど、その中でもリズムセッションのカッコよさは突出しています。先ほども書いた01『Kid Charlemagne』のドラムとベースの絡みは何度聴いても鳥肌が立つよ。 俺はこの作品を初心者に強くオススメします。凄く入りやすい作品だよこれ。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■AJA [1977] | ||
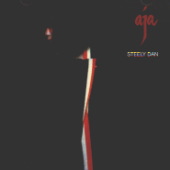 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| Steely
Danの最高傑作と名高い作品。実際それは事実だと思います。バンド形態を脱しロックバンドなどで見られるミュージシャン同士の絆みたいなものは完全に排除し最高の音楽を作る事だけに専念する事を目指してきたSteely
Danの音楽が究極の形を迎えた瞬間がこの作品なのでしょう。 それ故にそれまでの作品ではまだまだ残されていた生っぽさというのがかなり削られたある種の冷たさを感じる作風でもあると思います。そこで好みが分かれるとも言える訳で、最高傑作にして最高の問題作でもあるのではないでしょうか。この徹底して『考えられた』上で創られた音楽をさらに押し進めたのが次の『Gaucho』という事になるのだと思います。だけど、Gauchoよりもこの作品の方が『Steely Danの理想系』といえる出来。まったく隙の無い作品に仕上がっています。 感覚を重んじて楽曲を創るアーティストも多くいます。例えばジミヘンなんかはエフェクターマニアで知られていて、色々な実験的要素を試していた人ではありますが、彼は考え込んで創りこんでいくようなタイプではなく確実に感覚で音楽を創っていたタイプの人だと思います。それと比較すると、このSteely Danが目指していたモノはそれとは全く逆の方向である、というのがこの作品を聴くとよく分かります。 音像としては非常に音数が少なくなったのが特徴的です。かなり隙間を活かした音作りになっています。01『Black Cow』なんかは正にその特徴をよく表している曲ですね。02『Aja』も同じような印象の曲ではありますが、その冷めた雰囲気の中で突然展開されるスリリングなドラムソロが強烈に引き立ちます。これはジャズ的な要素というよりもプログレ的なモノすら感じる思い切った曲構成であると思います。そんな冷めた中にもダイナミズムをも盛り込むことに成功しているという点がこの作品と次の作品である『Gaucho』との決定的な違いだと思います。 03『Deacon Blues』では滑らかなメロディーラインを聴かせたりするのもまた良いですね。インストパートのクールさにも充分焦点が合わされていながらも03のような滑らかで素晴らしいメロディーも盛り込まれているのが素晴らしいです。音数が最小限に押さえられていて全く無駄の無い音作りなのに聴けば聴くほど新しい発見がある、というのも凄いです。 この作品はフュージョンやジャズが守備範囲であるリスナーにとっては馴染みやすい音である反面、ロックな人には非常に冷たく近寄りがたいモノだと思います。だけどそれで聴くのを止めてしまうのは勿体無さ過ぎると思うので、ロックな人もぜひ機会があったら面と向かって聴きこんでみてください。ここにはロック的な熱さはあまり無いですが、クールな知性で具体化されたロックとは違う『最高の音楽』を発見できると思いますから。 前作も初心者オススメ度はマックスだったけど、こっちもやっぱ名盤としてマックスだな。Steely Danにはじめて触れる人は前作と本作から入ればまず間違いは無いでしょうね。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■GAUCHO [1977] | ||
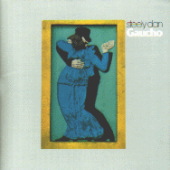 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| これはひとまずの最終作となった作品。後に20年の時を経て復活作を2000年にリリースすることになりましたが、持続的な活動としては一応最終作と言って差し支えないでしょう。 この作品は最高傑作であると言われる『Aja』と並ぶ傑作として名前が上がる事も結構あるようですが俺としてはSteely Danの作品の中で一番好きでないアルバムです。それは、前作で究極の形を披露した彼らがそれをもっと押し進めようとした結果、作りこみ過ぎて『Aja』にあった躍動感が完全に排除された感が強いからかな。あくまでも俺の好みの問題なのだけど、とにかく冷たい冷めた感じが苦手なのね。 『Aja』はそれまでのSteely Danの作品と比べるととても冷たい感じのする作風だと『Aja』の項でも述べたけど、それでも充分な躍動感やポップ感は生きていました。作品全体を包み込む完璧主義からくる計算して作り込むという精神と躍動感のある感覚を重んじた偶然性を精神とのバランスが素晴らしかった。例えば『Aja』収録の『Aja』においてのドラムの激しいソロではかなり思い切った曲展開をみせていたし、同じく『Aja』収録の『Decon Blues』、『Peg』、『I Got The News』などは冷めた中にも軽快なポップ感を兼ね備えていました。 しかし、この作品ではそれらの躍動感や軽快さよりもとにかく淡々とした印象が残ります。俺にはそれが聴いていて退屈に感じてしまう部分があるのです。俺はこれよりも2000年に発表された復活作の方が好きです。その復活作である『Two Against Nature』も同様に淡々としてるんですけどそっちの方がまだ好きなんですよね。どうしてか自分でもよく分からないんですけど。 なんつうか、本作の徹底振りに置いてきぼりを食らってしまったと感じたのかもしれません。それでも完成度の高さは認めますし、大好きな作品ではないにせよ、大嫌いな作品でもないとうのが正しいかな。なので個人的評価は結構低めの星二つ半。初心者オススメ度はロックな人の場合は星をマイナス一個、ジャズとかフュージョンに慣れ親しんでいる人、もしくはロックには特にこだわりが無いという人には星をプラス一個という感じかしら。 これは間違い無く評価が分かれる作品ですね。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| ■TWO AGAINST NATURE [2000] | ||
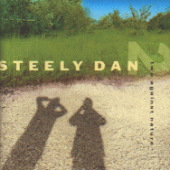 |
||
|
||
|
||
| 個人的評価 = XXX/100 初心者オススメ度 = XXX/100 |
||
| Steely
Dan名義としては実に20年振りのオリジナル・アルバム。 とても少ない音数とツルリとスッキリした音像が何処か聴き手をつき離すかのような作品となりました。ここにはかつて、多いにせよ少ないにせよ存在していたロックっぽさというのは殆ど感じる事が出来ません。そういう意味で『Gaucho』と同じ系統の作品といえますね。 フェイゲンのヴォーカルの粘着度がかなり薄めで、力を抜いたような歌い方が目立つのでより一層淡々とした印象を強めています。はじめから終わりまで同じリズムをずっと保っていくような曲が多いのでかなり平坦な印象。やはりここに躍動感というものは存在しません。そんな中に全体像を把握しづらいひねくれたメロディーが乗っています。そこがこの作品のポイントだね。01『Gaslighting Abbie』のメロディーが最もそれを象徴していて、単調なリズムの繰り返しの上に意外と複雑なメロディーが乗っているのよ。 初期の頃の計算された中にもロック的なラフな香りを感じさせた作風が気に入っている人にとってはとても冷たく突き放されてしまったような感覚を心地よくないと感じるかもしれないですね。俺はどうかというと、最初は非常に退屈に感じました。音数の少なさは前作『Gaucho』と同様で、歌の部分の音数もかなり少なく流れるようなメロディーというものがあまり無いという部分でも『Gaucho』と共通しています。メロディー自体が要所要所で途切れたようなモノが多くて、流れるようなメロディーが好きな俺にとっては聴いていてかなりもどかしく感じました。 しかし何度も聴くうちに前述したような単調なリズムの繰り返しが心地よく感じられるようになり、突き放されたような冷たさもジンワリと『味』に変わっていきました。なので今では結構好きだといえる作品。そして肝心な『らしさ』というのは、それなりに感じられます。他の作品と比べて全く変わってしまったわけではないのでご安心を。 しかし非常に淡々とした作風であるのは確かなのでやっぱり評価はわかれるに違いないですね。それとフェイゲンの歌がかなり弱々しいのも評価が分かれるところでしょう。年齢による衰えなんていう見解もあるようですけど、この淡々とした楽曲群を力強く歌われても違和感があるだけだと思うので、俺としてはこれで良いと思うし作風に合わせて『あえてそう歌っている』と解釈しているので個人的には全然気にならないな。 名盤であるという意見が多い『Gaucho』は俺個人はあまり好きな作品ではないです。この作品は『Gaucho』と同じような方向性を指し示しているのにも関わらず、何故か結構好きなのよね。こっちの方が曲調に愛嬌があるからかなあ。よくわかんねーけどとにかくこっちの方がすきなのっ。 総評としては、初心者がはじめてSteely Danに触れる場合に手を出すべきアルバムでは絶対に無いのは確かだけど個人的な評価としては20年振りの新作が『らしさ』をちゃんと保ちながらも、今までとは少し違うアプローチもなされているという点で充分満足できる作品だと思っています。その代わり今までの作品よりもずっと『聴きこむ』努力を必要としたけどね。 いやしかし音数少ねえアルバムだなあ。 [XXXX/XX/XX]
|
||
| DISCOGRAPHY INDEX▲ |
| BACK |